ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 内水面支場トップページ > 内水面支場のコンテンツ > 霞ヶ浦北浦・魚をめぐるサイエンス13
ここから本文です。
更新日:2022年8月9日
霞ヶ浦北浦・魚をめぐるサイエンス13
貧酸素水塊の形成とその被害
霞ヶ浦・北浦では、昭和48年と54年の夏季に網いけす養殖コイの大規模なへい死事故が起こりました。これは、下図のような機構による酸欠死であることかわかり、水温、溶存酸素量、風向風速などの測定から貧酸素水の発生を予測し被害の未然防止に役立てています。
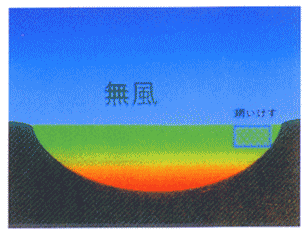
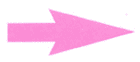
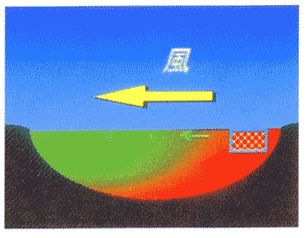
夏になり湖水が暖められると、冷たく重い水が湖底に停滞しやすくなります。富栄養化の進んだ湖では、植物プランクトンが著しく増え、それを分解するバクテリアの活動もさかんになります。このとき底層では、活発なバクテリアの呼吸によって酸素量の低下した水塊(貧酸素水塊)が発達します。水深の浅い霞ヶ浦・北浦では、この水塊が風の影響を受けて容易に浮上し、湖の風上側にある網いけすを襲います。
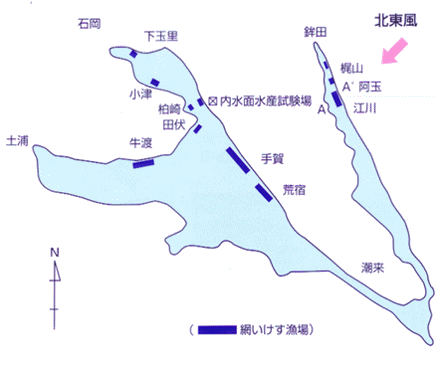
阿玉付近の溶存酸素量(ミリグラム/l)
昭和59年8月8日測定
A'側に酸素の少ない水が位置していることがわかります。
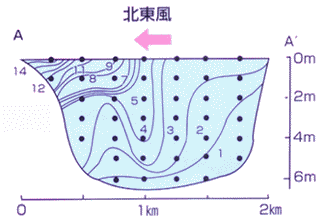
霞ヶ浦・北浦の主な網いけす漁場は上図のような位置にあり、北東風が吹いたときに被害を受けやすくなります。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
